Contents
周代の「采詩の官」
儒教の重要な経典である十三経のひとつである『周礼』は成立年代は戦国時代末期とされており、周代の官位制度を中心に文物・習俗・政治制度をまとめたものである。そこには周王朝の官職として誦訓・大師・象胥・小行人といったものがあり、それぞれに以下のような説明がある。
誦訓、掌道方志、以詔觀事。掌道方慝、以詔辟忌、以知地俗。王巡守、則夾王車。
(誦訓は、道方の志を掌し、詔を以って事を観る。道方の慝を掌し、詔を以って忌を辟く、以って地俗を知る。王巡守すれば、則ち王車を夾す)
誦訓とは各地の歴史や典故を司る官職であり、各地の古代の情勢を王に知らせる役目を担っている。また、各地の言葉の禁忌を知る責務もあり、王が禁忌を犯さないためにも各土地の習俗を調査する。王は各地を巡行する際には、自身の馬車の左右に誦訓の官を同伴させる。
大師、掌六律六同、以合陰陽之聲。(中略)大師、執同律以聽軍聲而詔吉凶。
(大師、六律六同を掌し、以って陰陽の声を合す。(中略)大師、同律を執りて、以って軍声を聴きて吉凶を詔す)
大師とは六律六呂と呼ばれる楽律を司り、森羅万象の音を調和させる。(中略)そして、大師は遠征の際には律管を用いて将軍の号令を聞き分けて吉凶を王に告げる。
象胥、掌蠻夷、閩貉、戎狄之國使、掌傳王之言而諭說焉、以和親之。
(象胥、蛮夷・閩貉・戎狄の国使を掌し、王の言を伝え焉に諭說し、和を以って之と親とす)
象胥は蛮夷・閩貉・戎狄からの国使の取り次ぎや対応を担当し、王の言葉を伝えて理解させる役割を担う。こうやって、彼らと意思疎通を図る。
小行人、掌邦國賓客之禮籍、以待四方之使者。
(小行人、邦国賓客の礼籍を掌し、以って四方の使者を待す)
小行人は各国の使者に関する儀礼を担当し、使者の歓待を担当する役割を担う。
いずれも何らかの形で言葉に関係する官職であり、地方を巡って習俗の採集を行う、儀礼に不可欠な楽律や音を司る、周辺異民族との歓待を担当する、外国からの使者をもてなす儀礼を担当する、といった職務であり、そこには雅言が中央語もしくは共通語として確立されている一方で、地方語や外国語(主に夷狄の語)を意識し、区別していたことが読み取れる。
『詩経』は周代の各地の詩歌を集めた中国最古の古典文学であり、詩歌を採集した目的は各地の民衆の声を聞くためであったという説もあり、これに関しては後漢の班個(32年~92年)らによって編纂された『漢書』「芸文志」に以下のような記述がある。
書曰、詩言志、哥詠言。故哀樂之心感、而哥詠之聲發。誦其言謂之詩、詠其聲謂之哥。故古有采詩之官、王者所以觀風俗、知得失、自考正也。
(書に曰く、詩言は志なり、哥詠は言なり。故に哀楽の心感ありて、哥詠の声を発す。其の言を誦するを之れ詩と謂ひ、其の声を詠むを之れ哥と謂ふ。故に古へに采詩の官有り、王たる者風俗を観る所以は得失を知り、自ら考へを正すなり。)
『書経(尚書)』には「詩言は志なり、歌詠は言なり」という一文があり、民衆の心中の喜怒哀楽があれば、それは歌に詠まれるものである。語を用いて表現するものを詩と呼び、歌声で表現するものを歌と呼ぶ。古代には「采詩の官」と呼ばれる役職があり、為政者は詩や歌から民衆の心中を推し量り政治の良し悪しを判断し、必要に応じて政治を直していくのである。
采詩の官が実在したかどうかについては研究者によって意見が分かれるが、各地の民衆の声をひとつの政治の判断材料にしていたのであれば、地方語すなわち方言はある程度は認知されていたはずである。これを裏付けることができるものとして後漢の応劭(?~204年)が記した『風俗通義』に以下の記述がある。
周秦常以歲八月遣輶軒之使、求異代方言。還奏籍之、藏於秘室。及嬴氏之亡、遺脫漏棄、無見之者。蜀人嚴君平有千餘言、林閭翁孺才有梗概之法。
(周秦、常に歳八月を以って輶軒の使を遣わし、異代の方言を求む。還りて奏し之を籍とし、秘室に蔵す。嬴氏の亡ぶに及び、遺脫漏棄し、之を見る者なし。蜀人厳君平に千余言有り、林閭翁孺に才かに梗概の法有るのみ。)
周と秦には八月になると使者を各地に遣わして、各地の言葉を調査させた。都に戻ってこれを奏上し、典籍としてまとめたものを厳重に保管していた。(秦の始皇帝が逝去して)その一族が滅びると、地方語の典籍は散逸し、これを読んで知ることができなくなってしまった。蜀の人である厳君平はわずかながらもその記録を保管しており、林閭翁孺もわずかとはいえ地方語についての概略を整理してまとめていただけである。
厳君平および林閭翁孺はともに揚雄の『方言』編纂にあたり大きく貢献した人物であり、『方言』は官途を求めて洛陽や長安に上京した地方出身者からそれぞれの地方語を聴取することで各地の方言をまとめていったとされており、同時にすでに散逸してしまっていた周代や秦代の地方の方言・童謡・歌戯といった記録についても両者が独自に収集記録していたものを参考にしていたと思われる。同時に厳君平と林閭翁孺の記録には秦代以前の地方語についての情報も残されていたとされる。
春秋戦国時代の方言
春秋戦国時代(紀元前770年~221年)は王位継承争いや権力者の政争で周王朝の権威が失墜した末、後に「戦国七雄(秦・楚・斉・燕・趙・魏・韓)」と称される諸侯の国が覇を競って中国各地に割拠する動乱の時代であった。諸子百家と呼ばれた思想家たちが富国強兵を進める各地の王に対して政策提案や外交を目的として全国各地を遊説した時期でもある。
儒家の孔子は山東省南部にあった魯の出身、孟子(紀元前372年?~290年?)も山東省南部にあったとされる小国・鄒の出身、同じく儒家の荀子は河北省南部の趙の出身、法家の韓非子(紀元前280年?~233年)は河北省北部・山東省南部・陝西省東部にあった韓の公子とされ、墨子(紀元前470年?~390年?)については魯・宋・楚など出身地に諸説があり、現在の中国における八大方言のように各地にはそれぞれの固有の地方語があったとされる。
当時活躍した思想家たちの母語はそれぞれ異なっていたはずであり、他の地方の人間との意思疎通のために何らかの共通語らしきものがあったのではないかと推定されている。春秋戦国時代の地域間の方言差を窺い知れるものとして以下のようなエピソードがある。
「秦伯師于河西、魏人在東。壽餘曰、請東人之能與夫二三有司言者。吾與之。」(『春秋左氏伝』「文公十三年」)
(秦伯河西に師し、魏人東に在り。壽餘曰く、東人の能く其の二三言を司るものを請ふ。我與に之く。)
(秦の康公が黄河の西岸に布陣し、対する魏は東にいた。そして、魏壽餘はこのように言った。「東の者でかの二三人の役人と話せる者をご用意ください。私はその者と共に行きましょう」)

「 今也南蠻鴃舌之人、非先王之衜。」(『孟子』「滕文公章句上 」)
(今や、南蛮鴃舌の人、先王の道を非とす。)
今は、モズの鳴き声ような理解不能な言葉である楚語を話す者(楚人の許行)は先王の道は非として何かを説いている。
「孟子謂戴不勝曰、子欲子之王之善與、我明吿子。有楚大夫於此、欲其子之齊語也、則使齊人傳諸、使楚人傳諸、曰、使齊人傳之」(『孟子』「滕文公章句下」)
(孟子、戴不勝に謂ひて曰く、子は子の王の善ならんことを欲するか。我明らかにし子に告げん。此に楚の大夫有りて、その子の斉語せんことを欲するや、則ち斉人をして諸に傳たらしめんか。楚人をして諸に傳たらしめんか。曰く、斉人をして諸に傳たらしめん。)
孟子は戴不勝にこのように述べた。「あなたは王が善であることを望みますか? 私ははっきりとあなたに伝えましょう。もし、ここに楚の士大夫がいたとして、その子に斉語を話せるようになってもらいたいとするならば、斉人にその教師をさせますか? それとも楚人に教師をさせますか?」 孟子はこう答えた。「斉人に教師役をさせます」と。
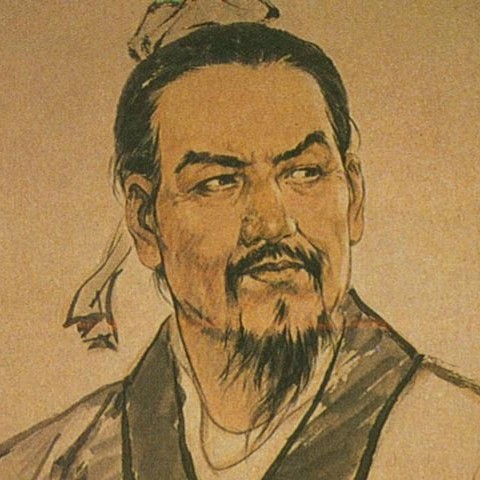
「孟子曰、否、此非君子之言。齊東野人之語也。」(『孟子』「萬章章句上」)
(孟子曰く、否なり、これ君子の言にあらず。斉東の野人の語なり。)
(孟子の弟子である咸丘蒙は「古代の帝王である舜が王位に就いた際に堯だけでなく実父の瞽瞍も臣下の礼をとって拝謁したので舜は恐れ謹んで落ち着かなかったと言い、孔子はこれを評して天下の人倫が乱れてしまいそうだと言ったそうですがそうなのでしょうか?」と問うと)孟子は答えた。「違う。それは君子の言葉ではない。それは斉の東に住んでいる野蛮人の方言だ」と。
「工匠之子、莫不繼事、而都國之民安習其服。居楚而楚、居越而越、居夏而夏。」(『荀子』「儒效篇」)
(工匠の子、子を継がざること莫く、都国の民その服に安習す。楚に居たりて楚たり、越に居たりて越たり、夏に居たりて夏たり。)
工匠の子は(その環境で生まれ育ったために家業を)継がずにはいられず、都市の住民は都市の服装を習慣として着ることを良しとする。楚の国に住めば楚人となり、越の国に住めば越人となる。中華に住めば、華人となるのである。
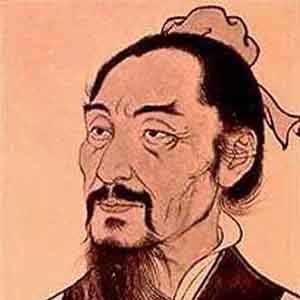
「吳王夫差將伐齊。子胥曰、不可。夫齊之與吳也、習俗不同、言語不通、我得其地、不能處。得其民、不得使。」(『呂氏春秋』「貴直論」)
(呉王夫差将に斉を伐たんとす。子胥曰く、不可なり。夫れ斉の呉と、習俗同じくせず、言語通じず、我其の地を得て処する能わず。その民を得て、使うを得ず。)
呉王夫差は斉を攻めようとしていた。そこで臣下の伍子胥はこう言った。「そのようにすべきではないでしょう。斉と呉の習慣や風俗は異なるだけでなく、言葉も異なります。その地を獲得しても統治することはできないでしょう。そして、その民を得ても治めることはできないでしょう。」

「鄭人謂玉未理者璞、周人謂鼠未臘者樸。周人懷璞過鄭賈曰、欲賣樸乎。鄭賈曰、欲之。出其樸、視之、乃鼠也。」(『戦国策』「秦策」)
(鄭人の玉の未だ理めざるを璞と謂ひ、周人の鼠の未だ臘ならざるを樸と謂ふ。周人璞を懐きて鄭賈を過ぎり、曰く、璞を買わんと欲するか。鄭賈曰く、これを欲す。その樸を出し、之を視るに、すなわち鼠なり。)
鄭人はまだ研磨されていない玉を「璞」と呼び、一方で周人は乾物になっていない鼠の肉を(同じ発音で)「樸」と呼ぶ。周人が「璞」を抱きかかえて、鄭から来ている商人を訪れて「璞を買おうとしているというのは本当か?」と聞くと、鄭の商人は「買いたいと思っている」と答えた。周人が「璞」を取り出して、鄭の商人がこれをよく見ると「樸」すなわち鼠の肉であった。
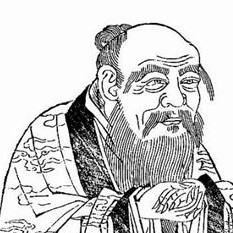
「楚人謂乳穀、謂虎於菟、故命之曰鬥穀於菟。」(『春秋左氏伝』「宣公四年」)
(楚人乳を穀と謂ひ、虎を於菟と謂ふ。故に之を命ずけて鬥穀於菟と曰ふ。)
楚人は乳を「穀」と言い、虎を「於菟」と言う。それゆえに(虎の乳で育てられたので)鬥穀於菟と名付けられた。
これらの逸話からは中央の権威ある言語すわなち共通語的なものがある一方で、地方語が中国各地に存在し、なおかつそれらはほぼ外国語同士のようなものであり、他地方の言葉の理解には習得が必要だったということが読み取れる。また、諸子百家のひとつである縦横家の蘇秦(?~紀元前284年?)は燕・趙・楚・韓・魏・斉に対して秦への対抗策として連合すること、すなわち合従連衡を伝えるために各国を遊説している。他の諸子百家同様に蘇秦には共通語の素養があったと同時に(蘇秦は洛邑出身である)、各国語も話せる語学力があったことが推測される。
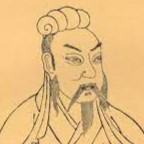
春秋戦国時代の後代にあたる漢代に揚雄(紀元前53年~紀元18年)が記した『方言』(正式名称は『輶軒使者絶代語釈別国方言』)は当時の各地の方言を集めた方言字書であり、同じ中国大陸でも同書が編まれた漢代の時点ですでに地方によっては言葉が異なるだけではなく、使用する漢字すら異なっているという認識が持たれていることが確認できる。揚雄は文官試験目的に都に集まった地方からの受験者から地方語を採集したとされ、整理が不十分で重複があるものの、首都周辺の秦・晋から、東は朝鮮、南は南楚(現在の湖南省周辺)に及び、当時の方言口頭語の記録としては非常に価値が高く、ここまで規模の大きい調査は明・清の異民族語彙を除いて比類がない。後世に至ると、『方言』は主として古典解釈学の資料として用いられることになった。
『方言』には
「党、暁、哲、知也。楚謂之党、或曰暁。斉宋之間謂之哲。」
(党・暁・哲は知なり。楚、これを党と謂ひ、或いは暁と曰ふ。斉・宋の間、これを哲と謂ふ。)
党・暁・哲とは(ある地方では)知(知る)という意味を指す。楚では「党」、もしくは「暁」と言う。斉や宋では「哲」と言うのである。
「嫁、逝、徂、適、往也。自家而出謂之嫁、由女而出爲嫁也。逝、秦晉語也。徂、齊語也。適、宋魯語也。往、凡語也。 」
(嫁・逝・徂・適は往なり。家より出ずるを嫁と謂ひ、女して出ずるを嫁と為すなり。逝は、秦晋の語なり。徂は、斉の語なり。適は、宋魯の語なり。往は、凡語なり。)
嫁・逝・徂・適とは、往(往く)という意味を指す。家から出ることを嫁と言うが、女性が(結婚して)他の家に行くことを嫁と言う。逝とは、秦や晋での言い方である。徂とは、斉での言い方である。適は、宋や魯での言い方である。往とは、共通語(洛陽方言)での言い方である。
というような用例があり、地域によっては漢字の発音どころか、特定の語(動詞や名詞など)で用いる漢字そのものが異なることを示唆している。
『説文解字』では筆を意味する単語の発音の方言間の違いを示している。秦では「筆(pįet)」、楚では「聿(i̯wǝt)」、呉では「不聿(pli̯wǝt)」、燕では「弗(pi̯wet)」であったとされる。上古中国語では「pli̯ǝt」であったとされ、これはチベット語のhbri-ba、ミャンマー語のrei-baに対応する(ミャンマー語ではbが脱落している)。また、ここから「筆」の語源は「書くもの」という動詞であったのではないかと推測可能である。つまり、上古中国語の音は「pli̯ǝt」がチベット語の書くもの「brids」に該当すると考えられるからである。語尾の-sは完了形(=連用形)で、名詞を構成している。チベット語では筆をsmyug-ma~smyug-maと呼び、これは書くもの、すなわち竹を意味している。チベットでは字を書くのに先端と尖らせた竹を使っていて、従来毛の付いた筆は使っていなかった。筆は秦の蒙恬(?~紀元前210年)の発明とされているが、実際に中国で使われだしたのは秦よりも以前であるとされている。古代中国語の筆は後にウイグル語・モンゴル語・満洲語に受け継がれ、現代モンゴル語では毛筆をüsün bir(毛の筆)と言い、üsünとは「毛の付いた」という意味である。
ただ、前漢当時は「方言」という名称はなく、「代語」「異国殊語」「殊語」「殊言」「異語」「異俗之語」といった語で方言や地方語といった概念を示していた。方言という語が生まれたのは後漢になってからであり、後漢の許慎(紀元58年?~147年?)によって記された『説文解字』の中で「方言」や「方語」といった語を使用しているのが確認できる。春秋戦国時代末期から前漢の間に編纂されたとされる『爾雅』も字義分類の字書であるが、『方言』同様に中国各地での方言単語も包括している(しかし、『爾雅』自体にはどの地方の方言かは明記されておらず、東晋の郭璞〔278年~324年〕が記した注釈書『爾雅註疏』に地方について言及した記述が見られる)。また、後漢末に劉熙(生没年不詳)によって記された辞典である『釈名』にも方言による単語の発音の違いを示している。
先秦の著作物の記述言語について触れると、中国最古の文学作品と扱われる『詩経』は殷方言・周方言(洛邑方言)とされ、同じく最古の文学作品である『楚辞』は楚方言、孔子の言行を記した『論語』は孔子の出身地である魯方言、秦漢の時代に至って秦(陝西省)と晋(山西省)の方言が通語すなわち標準語として定着し、「通語」もしくは「凡語」と呼ばれて雅言に取って代わっていったとされる。加えて、『方言』において秦晋方言が非常に多いことからも、秦漢時代には秦晋方言が共通語として機能していたことが窺い知れる。
