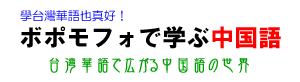台湾語とは
台湾語とは閩南語から派生し、台湾で独自に発達した方言である。17世紀から19世紀にかけて福建南部からの台湾に入植した人々の言葉が基礎となって広まったため、閩南語との類似点が多く見られる。台湾では「台語」(「台湾語」の略ではなく、「台湾閩南語」の略)と呼ばれ、この他別名として「ホーロー語(河洛語・福佬語)」とも呼ばる。
「台語」と呼ばれるのには、門構えに「虫」の字である「閩」の字が蔑称であるため、台湾に移住した各地出身者の言語が混淆したことで変質を遂げたため、中国では「閩」の字がいまだに使われており中国とイコールの関係であることを敬遠するとともに差別化するため、といった理由があるとされている。
台湾語と一言で言っても、台湾全土でその特徴が一様というわけではなく、地域によってそれぞれ特色がある。台南は漳州方言の要素(漳州腔)が強く、台北は泉州方言の要素(泉州腔)が強いとされている。とはいえ、一概にそれぞれ中国本土の漳州方言・泉州方言に全く等しいというわけではなく、数世代を経て漳州腔に泉州音的特徴が混じっていたり、逆に泉州腔に漳州音的特徴が見られる場合もある。台湾では台湾語のこのような特徴を「不泉不漳」もしくは「亦泉亦漳」と呼ぶ。とはいえ、台湾語の地域差は他の言語の方言と比較して大きなものではなく、相互理解に困難をきたすものではない。近年では台湾語の標準的な発音は高雄市および高雄周辺の方言とされており、台湾語の学習教材も高雄方言を採用していることが多い。
一方で台湾島以外に目を向けると、金門島では日本語の影響が少ない閩南語が、馬祖島では閩東語が話されて、烏坵島ではかつて莆仙語が話されていたものの、現在では台湾語が話されている。