台湾(中華民国)の住民は一般的に「台湾人」と呼ばれるものの、「台湾人」という単一の民族があるわけではなく、次のような人々(族群=エスニシティ―)で構成されている。「族群」とは文化や習慣が共通した集団を意味し、「民族」というよりは「アイデンティティをともにする集団」というニュアンスを含む。実際には使用言語によって分類されることが多く、そこに自分の意識(これを台湾では「認同」と呼び、「アイデンティティ」「帰属意識」といった言葉が適訳)が強く関わってくる。日常的な付き合いではあまり感じられないが、台湾の人々は自分がどの族群に属しているかを常に意識しており、これが社会に対しても深く作用しているとされている。
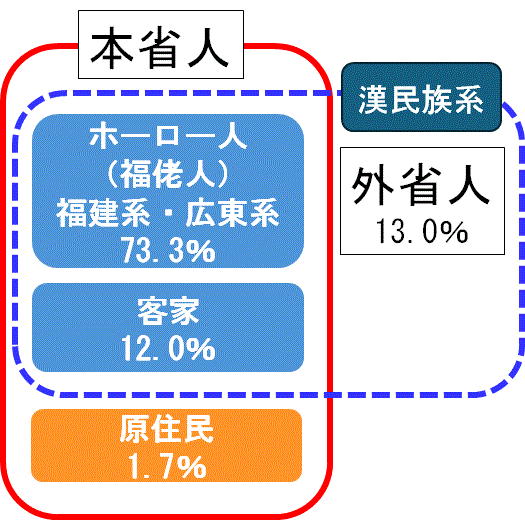
本省人
本省人とはすなわち「ネイティブの台湾人」といったニュアンスで台湾では定義されており、本省人は以下の3族群に分類される。
ホーロー人(河洛人・福佬人)
台湾総人口の約73.3%
16世紀頃から戦前までに台湾対岸の福建省を中心として中国大陸から移住した漢民族の子孫を指し、台湾のほぼ大半を占める人々で台湾語の主な話者。「有唐山公、無唐山嬤(中国人の祖父はいるが、中国人の祖母はいない)」という諺があるとおり、本省人はその歴史において原住民との通婚により混血が進んできた。また、ここには広東系の移民の子孫も含まれる。
客家
台湾総人口の約12%
漢民族のひとつと定義される人々で、元々は中国の中原(古代中国の都があった黄河中下流域)にいた漢民族が戦乱を逃れて各地を転々とした後に南方の広東省・福建省・江西省に移り住んだのが起源とされている。
原住民
台湾総人口の約1.7%
漢民族の台湾移住より以前に台湾に居住していた人々です。平地原住民と山地原住民に分類され、アミ族・パイワン族・タイヤル族・タロコ族・ブヌン族などがある。台湾では先住民のことを「原住民」と呼び、差別的名称とはならない。日本語での「先住民(先住民族)」は中国語では「すでに消滅してしまった民族」という意味になるので、ここでは台湾現地の呼び方に従って「原住民」の呼び方で統一する。なお、差別的に原住民を指す場合は、「山胞(山地同胞)」というように呼ぶことがある)。
原住民の詳細についてはこちらのページを参照。
外省人
台湾総人口の約13%
1945年の第二次世界大戦終結以後、とりわけ1949年の中華人民共和国成立により中国共産党に敗れた国民党を率いる蒋介石とともに中国大陸から台湾に移住した漢民族およびその子孫を指す。1945年の終戦による「光復」と同時に台湾が中華民国に編入され、それまでの日本による統治から中華民国による台湾の統治が始まった。これにより中華民国の中国人すなわち外省人が実質的な台湾の支配層となり、1987年の戒厳令解除まで公的な場での台湾語や原住民の言語の使用禁止など本省人への抑圧が続いた。現在では本省人と外省人の軋轢は政治面などで多少はあるにせよ少なくなってきているとされ、特に若い世代に至っては実生活面で本省人か外省人かの省籍を意識することの意義はほとんどなくなっている。古い世代では自身を「中国人」と呼んでいたのが、蔣経国(1910年~1988年)が戒厳令解除後の1987年に
「我在台灣住了四十年,是台灣人,當然也是中國人。」
(私は台湾に住んで40年、すでに台湾人です。もちろん中国人でもあります。)
と発言したように、外省人の中には「中国人」ではなく、「(明らかに中国大陸の中国人とは異なる)台湾で生まれた台湾人」という意識も芽生えるようになってきており、世代が下れば下るほどその傾向は顕著である。「台湾人である」という意識の点では本省人はほぼ同じであり、国民党の支持基盤が外省人ではあるが、本省人の会社経営者で中国大陸に工場を持つような場合には、台湾独立を掲げる民進党を選ぶのではなく、表面的であれ敢えて国民党を支持することで中国政府を刺激して不利益を蒙ることを防ごうとしている意図もあるとされる。
新住民
台湾人男性と結婚した外国人配偶者は「新住民」と呼ばれる。加えて、ここ数年において製造業・建設業・家政婦・介護職などを中心にフィリピン人・ベトナム人といった東南アジア系の外国籍労働者も増加してきている。
