Contents
中国に存在する方言間の差異
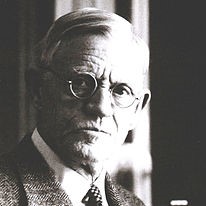
一般的に日本や欧米圏などでは方言(dialect)と言えば、その国の標準語に対しての各地方の言葉であり、方言間の多少の語彙や発音の違いはあるにせよ、それらは基本的に相互に理解できる程度の差異であり、お互いがそれぞれの方言で話しても意思疎通できるものである。
しかし、中国では方言とは「各地独特の言い回しや発音を具えた標準語に準ずる言語」という定義の認識ではなく、異なる地方出身者同士では全くコミュニケーションが取れないほど方言間の差異が非常に大きい地方語と定義される。
スウェーデンの中国学研究者ベルンハルト・カールグレン(1889年~1978年)はこれについて以下のように評している。
北京人が文語で書いた手紙を、広東人は即座に理解する。しかし、もし一方が北京語で他方が広東語で直接話し合うとするならば、この2人はあたかも、ベルリン人とアムステルダム生まれの人とが自国語で会話するとして、互いに理解しあえるほどにしか、お互の言うことが分からないのである。(カールグレン著『中国の言語』)
標準ドイツ語は西ゲルマン語群の高地ドイツ語に属し、オランダ語は西ゲルマン語群の低地フランク語に属する。どちらも同系統の言語ではあるが、文法的な違いの他に発音面でも明確な違いがあり、両言語の話者は辛うじて相手の言語で書かれた文章は何となく推測できるレベルであり、通訳なしの会話はまず不可能とされる。
ヨーロッパの印欧語の中でもドイツ語は地域間の方言差が特に大きいとされるが、中国ではその差異がそれ以上に大きく、異なる地方出身者同士は何らかの共通語(標準中国語)を使わない限りはお互いの方言のみで会話を成立させることは極めて困難である。状況次第ではもはや完全に外国語同士と呼んでも差し支えのないのが中国方言の最大の特徴と言える。
例えば、北京から地理的にわずか140km程度にしか離れていない天津市には天津語という方言があり、同方言は区分的には冀魯官話と北京官話の合流するような地域ではあるものの、明らかに標準中国語とは異なる方言である天津語を現地では使用している。
方言差の顕著な例として、福建省では同じ省内でも自分の集落の方言が山をひとつ越えただけの集落では通じないということは良く知られている。つまり、省内の方言間差異が他省以上にはるかに大きいのが福建方言の特徴である。厦門市で話される厦門語(閩南語に属する)と、厦門市から約370km離れた福州市で話される福州語(閩東語に属する)とではお互いの方言を話す者同士では標準中国語なしでの意思疎通は不可能と言われるほど異なるとされ、その中間にある泉州市(厦門市から約100km)で話される泉州語も厦門語と同じく閩南語に属しているが、同様に両者は全く異なるとされる。
閩南語に分類にされる海南語に至っては、13世紀の南宋の時代に派生したその成立過程で独自の変化を遂げていったために福建省の閩語話者でも理解できないほどになっている。また、福建省内の閩語話者はその母方言によっては閩南語の変種とされている台湾語を全て理解できるわけではないが、台湾語話者の言っていることは何となくニュアンスが理解できることもあるという。反対に台湾語話者も福建省内において地域によってはその閩語での発話がある程度は理解できることもあれば、何の問題もなく意思疎通ができるケースがある。
これに類似した事例は、揚子江周辺(長江下流域)の呉語にも存在している。揚子江の南岸、上海から南京までの江南と呼ばれた地域は古来より「百里不同風、十里不同音(百里違えば風俗習慣が異なり、十里違えば発音が違う)」と形容されるほどに、クリーク(堀割り・川)で網の目のようにくぎられ、交通の不便さが長い年月をかけて方言の乖離がひどくなって固定したことで、隣村同士でも言葉が通じないという現象が生じた。
呉語には下位方言に上海語・蘇州語・寧波語・紹興語などがあり、特に浙江省温州市で話される温州語は他の呉語話者でも理解するのが難しいどころか中国の中で最も難解な方言とも言われている。温州語は分類上は呉語とされるものの、地理的に福建省に近く(福建省と浙江省の省境にあり、一番近い福建省の寧徳市までは約234km程度の距離しかない)、歴史的に福建省の他地域同様に温州市も古くは紀元前に楚に滅ぼされた越の後継国家であった東甌に属していたこともあって温州市に相当する地域は閩語の影響を少なからず受けてきたとされる。そのため、台湾語のできる台湾人は一部では温州語を3~4割程度理解することができるとも言われている。
1979年に勃発した中越紛争では緒戦で人民解放軍が二個師団程度壊滅させられたのはベトナム軍がベトナム戦争で接収した米軍のハイテク兵器を使用したのが主要因とされているが、元々は地理的に近い位置に配備されていたチワン族通信兵の話すチワン語がベトナム語に非常に似ていることから傍受された無線通信が解読されてしまい、その代わりに温州語が少数言語による非暗号化無線通信(コードトーカー)として利用されたという俗説がある。ただし、両言語とも歴史的に強く中国語の影響を受けて続けてきているものの、チワン語はタイ語と同じタイ・カダイ語族であり、ベトナム語はクメール語(カンボジアの公用語)と同じくオーストロアジア語族に属するものとされ、言語系統的には同じではない。
また、中華民国の建国の立役者で初代臨時大総統であった孫文(1866年~1925年)は現在の広東省中山市出身の香山語(広東語の下位方言)話者、同じく中華民国の総統であり国民党を率いて中国共産党と対立した蒋介石(1887年~1975年)は浙江省寧波市出身の寧波語話者、中華人民共和国を建国した毛沢東(1893年~1976年)は湖南省韶山市出身の韶山語(湘語のうち訛りの強い老湘語の下位方言)話者、文化大革命後の荒廃した中国の再建として改革開放路線を推進した鄧小平(1904年~1997年)は四川省広安市出身の客家語話者(鄧小平の出自は客家)と、近現代中国の指導者はほぼ全員が中国標準語のネイティブスピーカーであったわけではなく、むしろ彼らの母方言を公的な場でも常用していた。中でも毛沢東の話す湖南省方言の湘語は極めて独特のアクセントがあったために同じ中国人であっても聞いても理解できずに通訳者を介していたのは有名な話である。
なお、中国大陸で標準中国語教育が徹底される以前(1950年頃)は、中国向けのNHKの対外放送の中の放送言語には北京語(北京方言)以外に、広東語・閩南語があったとされている。
中国の方言
現在中国には七大方言もしくはこれに三方言を加えた十代方言があるとされている。
七代方言
官話方言
華北北方官話
北京官話
話者数:約2,676万人)
使用地域:北京市
東北官話
話者数:約9,802万人
使用地域:黒龍江省、吉林省、遼寧省、内蒙古自治区の一部
冀魯官話
話者数:約9,000万人
使用地域:天津市、河北省南部、山東省西部、北京市平谷県、山西省広霊県
膠遼官話
話者数:約3,000万人
使用地域:山東省膠東半島(青島市、煙台市、威海市など)、 遼寧省遼東半島(大連市、鞍山市、丹東市、営口市、遼陽市など)
西北官話
中原官話
話者数:約1.86億人
使用地域:河南省、陝西省関中、山東省南部、江蘇省、安徽省、山東省、河北省、河南省、山西省、陝西省、甘粛省、青海省、寧夏回族自治区、新疆ウイグル自治区
蘭銀官話
話者数:約1,000万人
使用地域:甘粛省、寧夏回族自治区、内蒙古自治区、新疆ウイグル自治区
西南官話
話者数:約2.6億人
使用地域:四川省、重慶、雲南省、貴州省、湖北省西部、湖南省北西部、広西壮族自治区、陝西省南部、甘粛省南部、江西省の一部
江淮官話
話者数:約7,000万人
使用地域:南京市、江蘇省鎮江市句容市、安徽省馬鞍山市、江蘇省中部、安徽省中部、湖北省東部、江西省北部
呉語
話者数:約8,700万人
地用地域:上海市、江蘇省中南部、浙江省、安徽省南部、江西省の一部、福建省の一部
主な下位方言:上海語(約1,000万人)、蘇州語、紹興語、寧波語、台州語、温州語
広東語(粤語)
話者数 約3,000万人
地用地域:香港、マカオ、広東省、広西チワン族自治区の一部
主な下位方言:香港語、広州語、中山語、広西語、台山語
贛語
話者数 約2,000万人
地用地域:江西省中部・北部、湖南省東南部、福建省西北部、安徽省の一部、湖北省の一部
主な下位方言:南昌語
湘語
話者数 約3,600万人
使用地域:湖南省、広東省北部、広西チワン族自治区北部、四川省の一部
主な下位方言:長益語、婁邵語、衡州語、辰漵語、永全語
閩語
話者数 約7,000万人
使用地域:福建省、広東省、台湾、シンガポール、海外の華人コミュニティ
主な下位方言:閩北語⇒建陽語
閩東語⇒福州語、福安語、蛮講
閩南語⇒閩台グループ(泉州語〔話者数:約700万人〕、漳州語〔話者数:約400万人〕、厦門語〔話者数:約150万人〕、
台湾語〔話者数:約1,874万人〕)
浙南グループ(浙南語)
潮汕グループ(潮州語〔話者数:約1,400万人〕)
雷瓊グループ(雷州語、海南語〔話者数:約110万人〕)
莆仙語⇒莆田話、仙遊話
閩中語⇒三明語、永安語、沙県語
客家語
話者数:約3,400万人
使用地域:広東省東部、福建省西部、広西省南部、台湾、四川省、湖南省、広西チワン族自治区、海南省、浙江省南部、海外の華人コミュニティ
主な下位方言:贛州客家語、粤北客家語、潮汕客家語、潮漳客家語、汀州客家語
台湾客家語(四県腔〔苗栗腔〕、海陸腔〔新竹腔〕、大埔腔〔東勢腔〕、饒平腔、詔安腔)
十大方言
近年新たに以下の三方言を上記七大方言と同列に扱い、十方言と扱うべきとの議論がある。
晋語
話者数 約6,300万人
山西省、陝西省北部、河北省西部、内蒙古自治区西部、河南省の一部
主な下位方言:并州語、呂梁語、上党語、五台語、張呼語、大包語、志延語、邯新語
徽語
話者数: 約320万人
使用地域:安徽省南部、安徽省に隣接する浙江省・江西省の一部
主な下位方言:績歙語、旌占語、休黟語、祁徳語、厳州語
広西平話(平話)
話者数: 約230万人
使用地域:広西チワン族自治区、湖南省の一部
主な下位方言:桂南平話、桂北平話、通道平話、紅瑤平話、融柳平話
この他にも、ドンガン語(東干語)もこの中に加わるべきという議論もある。ドンガン語とは1862年に清朝に対して反乱を起こしたものの失敗したウィグル人(中国系イスラム教徒)が居住地であった現在の陝西省からロシア帝国領内に逃亡し、カザフスタン・キルギスに定住した結果、その子孫がドンガン人(東干人)と呼ばれるようになり、彼らの話す言語がドンガン語と呼ばれるようになった。ドンガン語には陝西系と甘粛系の二系統が存在しており、甘粛系が標準的なドンガン語とされ、キルギス首都のビシュケクやカザフスタンのジャンブール州で話されている。陝西系は主にキルギス北部のトクマクやカザフスタン・ウズベキスタンの一部に分布している。
ドンガン語自体は甘粛方言や陝西方言が属する西北官話由来であり、標準中国語を熟知していればおおむね理解可能である。声調は4声もしくは3声で、旧ソ連圏であるためにキリル文字で表記されるのが一般的である。そして、文字の性質上声調符号を施さないのが通例であることから単語を見ただけでは同じ綴りで異なる発音や異なる意味の判別がしづらい。また、中国の回族で話される中国語同様にアラビア語・ペルシャ語・テュルク系言語から借用語を多く含むほか、地理的にメジャーな言語であるロシア語の語彙も取り入れられている。
中国方言の現在位置
中国では古来より方言同士では意思疎通が困難という認識が持たれつつも、これを何らかの政策をもって改善しようという試みは行われてこなかった。辛うじて、清代に入って清朝第5代皇帝雍正帝(1678年~1735年)により官界で広東省や福建省出身の官吏が活躍する機会が増えてきたことから、官話すなわち現在の標準中国語の原型とも言える言語を話せることが官吏として登用する条件にした他、そのために官話の学校を設立したり、教科書の編纂を行った。これは言語政策として成功したとは言い切れないものの、これが功を奏して浙江省との省境にある福建省省浦城県は呉語と閩語が入り組む土地にも関わらず官話島として残った事例もある。
言語の統一化という中国の至上の命題は1949年の中華人民共和国建国によって達成され、標準中国語=漢語が中国大陸全域に普及し、これを用いて異なる地方出身の中国人同士でも容易に意思疎通ができるようになった。台湾でも中華民国が台湾島を含めた実効支配する領内で実施した国語化政策により、台湾島内の多民族・多言語の社会に標準中国語の普及に一定の成果を出している。
逆に言えば、中国大陸の言語環境は総じて方言差が大きすぎるが故に、基本的には各方言のネイティブスピーカー以外はよほど特殊な事情がなければほとんど話すことも聞き取ることもできないのが実際の姿である。例えば、標準中国語も上海語も話せる上海人は何もしていない自然状態では必要に迫られて学習しない限りは広東語を話すことも、聞いて理解することもできないということを意味する。その反対の状況として、香港人が広東語も標準中国語も話せたとしても、自然と上海語を話せるということはまずあり得ない。
しかし、漢字は各方言でおおむね共通しており、程度の差はあっても書き言葉=文章語であれば、知らない方言であっても中国人は読解することは比較的容易である。中国大陸でも台湾でも使用言語が標準語であっても方言であってもテレビではほとんどの番組で標準中国語の字幕が施されるのが一般的であり、他方言の単語や発音に対してへの理解のアプローチがしやすくなっているのも事実である。
各地に方言が存在するという事実はあるのは客観的事実だが、中国大陸や台湾では若年層で方言を話せなくなっているという事象も散見されている。例として、上海市では上海語を話せない若年層が増えており、台湾でも同様に台湾語を話せない本省人や客家語を話せない客家の若年層も増えてきている。台湾について言えば、標準中国語しか話せない孫は、標準中国語を話せず台湾語しか話せない祖父母と全く意思疎通が取れないことが台湾の本省人の家庭では見られることが散見される事例も存在している。
上海市では上海語が衰退しつつある現状から保護と継承が必要という認識が高まり、一部路線バスや市営地下鉄で上海語のアナウンスが放送される他、上海浦東国際空港でも上海語による搭乗アナウンスが流れるようになった。また、これまでは上海語の映画やドラマは制作・放映されることは極めて少なかったが、近年上海語のテレビドラマも製作されている。
台湾では1995年の初の民主化選挙により、李登輝(1923年~2020年)が総統に当選すると、初めて台湾そのものに焦点を当てた郷土言語(2016年からは「本土語文」に改称)が行われるようになり、それまでは公教育や公的な場での台湾語はほぼ禁止で標準中国語のみが事実上認められていたのが一転して、台湾語や客家語が公教育の場で指導される場面が増えるようになっていった他、テレビやラジオなどのマスメディアでも台湾語で放送されることが一般的になってきた。同時に台湾の原住民についても原住民認定される一方で、その言語の保存や継承についても議論される場が増えてきている。
